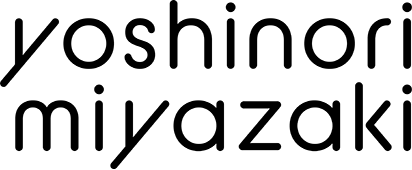2020年5月14日
いろいろなショップに似たようなデザインの服が並ぶ理由

例えば、新宿ルミネに足を運び、あるフロアの同じゾーンのブランドのお店を見比べると、似たような服が並んでいると感じたことはないでしょうか。
あるショップのスカートを、近くのショップの店頭に飾っても、違和感がないのではと思ったことはありませんか。
私が某ブランドで、洋服の企画デザインをしていたころ、洋服の商品開発は以下の手順でルーティン化されておりました。
パリコレ等のコレクションが開かれた数週間後、日本ではWWD等がファッションセミナーを開催します。
著名なファッションジャーナリストやバイヤー等がパリコレなどの内容をまとめ、次のシーズンのトレンドなどをレクチャーします。
セミナーの内容は概ね、コレクションの傾向を最大公約数化したようなものとなります。
具体的には、例えば、花柄、水玉柄が多く出されたとか、フェミニンな要素が強かったとか、コーラル系のカラーが目立ったなどです。
これらのコレクションセミナーには様々なブランドのMDやデザイナーが出席します。
日本のファッション商品の作り手たちが一堂に会したセミナーで、みな同じ情報を受け取り、そこから用意ドンで次のシーズンの商品作りがはじまります。
同時に、他社がどんなデザインやアイテムを作っているか、出入りの商社や生地屋を通じて情報が駆け巡り、ブランドごとに次シーズンのテーマが決められ、展示会に向かってサンプルが作成されます。
展示会では、そのブランドの次シーズンのテーマと商品が発表され、そこに招かれたファッション誌の編集者やスタイリスト、百貨店等のディベロッパーさんやバイヤーさんの反応を伺います。そして若干の修正が加えられ、場合によっては同質化の傾向が強まった商品が量産され、店頭に並びます。
その後シーズンに入ると実際の結果がわかります。
花柄は売れたけど、水玉はダメだったとか、○○社の××は売れているという情報が繊研新聞をなどを通じて業界を駆け巡ります。
こうして、みんなでリスクを回避しながら売れ筋商品を求めて、他社で売れた同じような商品の期中対応生産が始まります。
これらの繰り返しによって、いくつかのショップでは似たような商品が店頭に並び、流行として皆同じようなデザインやコーディネートの服を着るようになります。
この時、逆に流行っていないデザインの服を探すことは難しいかもしれません。生産していないので、選択肢が無いのです。
余談ですが、流行っている洋服やデザインが、必ずしもすべての人に似合うわけではないので、注意が必要です。
例えば、2010年頃にはやったガウチョパンツは、手を変え品を変え、数年前にドレープパンツなどの名前でまた流行りましたが、このパンツは、身長が低くヒップが大きめの人は、バランスがとりづらく、似合わないことがあります。
どうしてもこのアイテムを着たい場合は、ウエスト位置を高めにマークし、着丈もくるぶし丈にして、トップスはショート丈で軽めにすると、バランスが整えられるかとおもいます。こんな時、オーダーメイドを活用すると、すべてのアイテムを最適な比率にアジャストできますので、機会があればお試しください。
 一覧へ戻る
一覧へ戻る